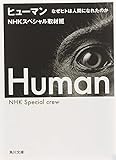
- 作者: NHKスペシャル取材班
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2014/03/25
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (1件) を見る
はじめに 心——この不可思議なもの
第1章 協力する人・アフリカからの旅立ち 〜分かち合う心の進化〜
第2章 投げる人・グレートジャーニーの果てに 〜飛び道具というパンドラの箱〜
第3章 耕す人・農耕革命 〜未来を願う心〜
第4章 交換する人・そしてお金が生まれた 〜都市が生んだ欲望のゆくえ〜
おわりに なぜいまヒューマンなのか
4章だけは期待外れだったが(頻繁に書き手の自意識が透けて見えて「絶対これ女性が書いているよな……」と思ったらやっぱり女性だった)、特に1章は凄く面白かった。
山本真也博士の研究
例えば、京大霊長類研究所の山本真也博士の研究。山本博士はチンパンジーを使った実に興味深い実験をしている。長くなるが、引用したい。
隣り合うふたつのブースに、それぞれチンパンジーを入れる。ふたつのブースには、異なる課題が仕組まれている。片方には、ストローを使わなければジュースを飲めない容器が置いてあり、もう片方には、ステッキを使って引き寄せないとジュース容器が取れないという状況になっている。しかも、ストローが必要なチンパンジーのブースにはステッキがあり、ステッキが必要なほうにはストローがある。つまり、必要な道具が逆転しているという状況にしてあるのだ。お互いに協力しなければ、両者ともジュースを飲むことはできない。
協力ができるよう、ブースを仕切るパネルには、縦12.5センチ、横35センチの穴が空いている。道具のやり取りができるわけだ。(略)
このような状況で、穴を通して行われるやりとりを調べた。
以下は実験結果とその考察である。
観察の結果、全体の59%において、道具の受け渡しが見られた。つまり、困っている相手に対して道具を差し出したのだ。疑い深い人なら、「遊びでやっているのではないか」と突っ込むところだが、そんな突っ込みに対する反論も山本さんはきちんと調べていた。相手が道具を必要としていない場面では0.3%しか受け渡しは見られなかったのだ。つまり、遊びで渡しているのではなく、相手が必要としているから渡していたと推定できるのだ。
ただし、細かく観察すると、受け渡しの74.7%は、相手の要求に応じる形で起こっていた。たとえば、ステッキの欲しいチンパンジーが、ステッキを持っているチンパンジーに対して、道具を要求する。穴から相手に手を差し伸べ、道具を要求する。相手がなかなか渡してくれないと、パネルや手を叩いたり、声を出したり、道具を持っている相手の注意を引こうと懸命だった。たいていはこのように要求されて初めて、道具を差し出したのだ。
山本さんはこの実験の要点をこう話してくれた。
「チンパンジーの利他行動には、相手からの要求が重要なようなんです。ヒトは他人が困っているのを見ると、頼まれなくても自ら進んで助けることがありますが、チンパンジーは相手からの要求があって初めて助けることが多い。実際、手の届かない場所に置かれたジュースの容器に必死に手を伸ばす相手を見ても、持ったステッキを自発的に差し出すことは希(まれ)なんです。頼まれれば応じるが、自分から進んでお節介を焼くことはない。これがチンパンジーの利他行動の特徴かもしれないと思うんです」
もうひとつ、大きな特徴があった。山本さんは、片方のチンパンジーしか道具を持っていない状況でも実験を行った。(略)
こうした場合(引用者注・何の見返りもない状況)でも、チンパンジーたちは要求されれば道具を渡す行動は継続した。まさに利他行動がチンパンジーにもあることを示している。
引用部分の下線は引用者による。(以下、全て同様)
この後この研究は、ヒトとチンパンジーの心のありようの違いに踏み込む、さらに興味深い実験を重ね、素晴らしい展開を見せる。これ以上書くと本書を読む楽しむが減るため、この辺にしておくが、敢えてキーワードを書くと、チンパンジーとヒトとの違いは「チンパンジーは、助けるが、助け合わない」ということだ。それが何を意味するのかは本書を読んでほしい。面白さに興奮すること請け合いである。
ベン・シーモア博士の研究
もうひとつ、ロンドン大学のウェルカム・トラスト神経画像化研究センターのベン・シーモア博士の研究も実に興味深かった。彼はどういう相手に対して「痛みの共感」が生じるのかを、様々な実験で調べているそうだ。例えば、映画の主人公が敵対する登場人物から殴られたときに、自分が殴られたわけではないのに何となく嫌な感じが残る……これが典型的な痛みの共感である。
そうした「痛みの共感」を調べるために、被験者に電気ショックを受ける他人を見せ、その脳活動を測定する実験をしているのだが、ある実験では、痛みを受ける「他人」に仕掛けを持たせている。二つのケースを準備するのだが、一つ目のケースは被験者が「公正な人」と思っている他人が痛みを受け、二つ目のケースは被験者が「不公正な人」と思っている他人が痛みを受けるのだ。
実験の狙いをシーモア博士はこう語った。
「私たちには、自動的に他人に共感する能力があります。特に友人や家族のように自分の大切な人が痛みを感じているのを見るのは、本質的に不愉快なことのようです。この能力は先天的に、あるいは幼少時に発達すると私たちは考えています。そこで、人は誰に対しても自動的に共感するものなのかどうか、その点を探求したのです」
公正というプラスの評価をしている相手が痛みを受けている場合でも、不公正というマイナスの評価をしている相手が痛みを受けている場合でも、同じように心の痛みを感じるのだとすれば、共感というシステムはきわめて画一的に働くということになる。
逆に、二つのケースで被験者の脳活動に差があれば、共感は相手次第で働いたり、働かなくなったりする、きわめて恣意的なものということになる。
共感が本当に自動的なシステムかどうか、シーモア博士は明らかにしようとしたのだ。
実験内容の詳細は省くが、要は、俳優を雇って被験者と共にゲームを行い、ゲーム中の俳優の振る舞いで「公正な人」と「不公正な人」を被験者に強く印象づけた後、その俳優が電気ショックを受けるという映像を被験者に見せるのである。そして痛みに共感する、つまり不愉快な気持ちを抱いたときには脳の「前頭皮質」という部分が強く活動するという結果が得られる。
結果ははっきりしていた。
「公正な人の痛みを見たときに強く活動し、不公正で利己的な人の痛みを見たときにはまったくといってよいほど活動がありませんでした。すなわち、過去に自分に対して利己的な態度を取った者の痛みを見るとき、共感に関わる脳の活性化は見られないのです」
つまり、共感は思っていたほど自動的ではないということだ。
人間は共感する能力を持っているといっても、必ず共感するわけではない。共感して自己犠牲を厭わず行動する場合もあれば、まったく共感せずに冷ややかに黙殺している場合もある。(略)
……と、ここまではまあ想像の範囲内だが、ここからがシーモア博士の研究の真骨頂と言うべき恐ろしい成果である。
シーモア博士たちが注目していた脳の場所は、もうひとつあった、側坐核と呼ばれる場所だ。
側坐核は脳の報酬回路の一部だと考えられている。報酬回路は人間が快感を得るための行動を喚起する。つまり、この領域が活性化すると、快感を感じたということになる。
この側坐核の活性にも、大きな差が出たのだ。
不公正な人の痛みを見たときには、共感に関わる脳の領域が活性化しなかったことに加え、この側坐核が活性化したのである。逆に、公正な人の場合は正反対だった。共感部分が活性化した代わり、側坐核は活性化しなかったのだ。
そう、分かったのは、私たちの脳に潜む驚くべき二面性だ。私たちの脳は、不公正な人、つまりは不愉快な、嫌な人の痛みを見たときに、快感を感じるのである。
冷静なシーモア博士も少し興奮気味に語った。
「私たちの脳には、不公正な人に対する天罰の意識が報酬回路に付加されているようです。社会的な行動を行う私たちホモ・サピエンスは、不公正な人の搾取から自らを守る必要があります。それゆえだと思います」
自らを守るために、なぜ快感まで感じる必要があるのだろう。
「不公正な彼らが社会で勢力を得れば、協力という美徳が崩壊します。だから、社会を保護するため、罰という手段が必要です。その罰をきちんと行うため、人を罰したいという本質的な欲望が必要です。この結果を見れば、それは、相手の痛みを見る快感がもたらしている可能性があると思います」
共感の能力は、その力が発揮される場合と、されない場合があるというだけでなく、他人の不幸を密の味と感じてしまうこともあるというのだ。
こちらもこの辺にしておこう。
実は2章と3章にも面白い実験や考察が盛り沢山で、引用しまくりたいのだが、キリがないのでやめておく。学校で習った「農耕が始まったから定住が始まった」みたいなのもどうやら間違いだと近年の研究ではわかってきているとか、とにかく面白い発見に溢れた本である。
大推薦!!