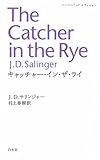
キャッチャー・イン・ザ・ライ (ペーパーバック・エディション)
- 作者: J.D.サリンジャー,J.D. Salinger,村上春樹
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 2006/04
- メディア: 新書
- 購入: 11人 クリック: 73回
- この商品を含むブログ (177件) を見る
俺は野崎孝訳『ライ麦畑でつかまえて』は読んだことがない。もちろん名作かつ名訳ということは知っていたが、書名と「青春小説の金字塔」という評判を知るにつけ、「うふふ、私をつかまえてごらんなさいよー」「ははは、待てよー」という腐れ落ちた恋愛小説を勝手に想像してしまい、敬遠していたのである。しかし俺の好きな村上春樹による新訳が出たので読んでみたところ、その勝手な思い込みは良くも悪くも裏切られた。
主人公ホールデンは、そんな恋愛小説に出てくる主人公とは似ても似つかない。授業をサボり、予習もせず、試験も真面目に解答せず、16歳なのに既に3回目だか4回目だかの高校放校処分となっている。酒やタバコもたしなむ。金持ちのボンボンで、貧乏人を馬鹿にして、友達を馬鹿にして(これについては友達にも原因がある)、人の話を全く聞かない。そして同じ失敗を繰り返す。小説の前半は正直「これのどこが青春小説の金字塔なんだろう」と思いながら読んでいた。
ただ、読み進めるにしたがって、ホールデンに対して複雑な、しかし痛切なまでの感情を抱くようになった。ホールデンには確かに人間的に大きな問題がある。そして(一読しただけなのではっきりとした自信は持てないまでも)どうもホールデンは分裂症的とも躁病的とも取れる精神的なトラブルを抱えているように見える。そして現実問題としてホールデンは社会と上手く折り合いをつけられていない。けれどホールデンは、何とか折り合いをつけようとしているようにも見えるし、折り合いをつけようとできない事実に対して苦闘しているようにも見える。複雑な主人公であるが、ひとつ言えることは、ホールデンは彼なりに必死なのだということである。これはホールデンというまだ何者でもない少年の「自己葛藤」の物語であろう。今の俺は(様々な現実的な問題はあれど一応)社会人として社会と折り合いをつけることができているが、もっと子どもの頃に読んだ方が感動も大きいような気がする。できれば俺自身まだ何者でもない中高生や浪人生の頃、あるいは精神的に深い葛藤を抱えていた大学生の頃に読んでおきたかった。
続けて、本書を読んで気になったことを幾つか書き留めたいが、それもやはりホールデンという少年についての印象だろう。ホールデンが留保なく愛する人間は、もう死んでしまっている弟のアリー、理想的に過ぎる妹のフィービー、そして一昨年の夏の間だけ隣に住んで仲良くしていたが今は会っていないジェーン・ギャラガーである。この3人の共通点は、3人ともリアリティに乏しい登場人物だという点だ。アリーは現実問題として既に死んでいるし、フィービーは理想的に過ぎるあまりちっとも現実味がない。ジェーン・ギャラガーも一昨年の夏に会ったきりだ。ホールデンはジェーンに会いたい会いたいと言っているのだが、実際は腰が重く、一度ジェーンの家に電話をして母親が出たら電話を切って、それっきりである。ホールデンはジェーンそのものではなく自分の記憶の中のジェーンを愛しているようにも見える。結局、ホールデンは変わらないイノセント(純粋無垢)なものだけを留保なく愛しているのである。
それでいて、ホールデンが留保なしで愛せないものや、心の中で馬鹿にしているようなものに対しては、腰も口も軽い。美しいが深い精神性など持ち合わせていないサリー・ヘイズには簡単に電話をかけてデートをしているし、大して可愛くもない3人組の田舎娘をナンパしている。電車で隣り合わせた人にペラペラと嘘の話を並び立て、全く乗り気でないカール・ルースを呼び出して(向こうは明らかに迷惑しているにもかかわらず)ペラペラと喋り続けている。元ストリッパーの女にも電話をしているし、ホテルでは娼婦を頼んでいる。それでいて、いざ「やれそう」となると、どちらもビビって拒絶しているのである。孤独感が非常に強いのだが、深い触れ合いは恐怖の対象だというようにも見える。
その証拠というべきか、夜中に電話したのに嫌な顔ひとつせず家に泊めてくれたアントリーニ先生に対して、寝ているときにアントリーニ先生が頭を撫でていただけで、ホールデンは恐怖のあまり家の外に飛び出している。ホールデンはゲイ的なものを感じ取ったのだが、本当にアントリーニ先生がゲイなのかは判断つかなかった。ホールデンのことを心の底から気にかけてくれている先生が、我が子の頭をさするようにホールデンの頭を撫でるというのは、十分に有り得ると思えたからである。それに仮にアントリーニ先生がゲイだとしても、先生は夜中なのにホールデンを快く迎えてくれるほどホールデンのことを気にかけてくれている。ここまで親切にしてくれているのだから、同性愛的な関係の強要がないのであれば、別にゲイでも良いだろうという気もする。俺なら敬愛する先生がゲイでも別に構わないけどな。まあ現代日本とは時代的・社会的な違いがあるから一概には言えないけれど、いずれにせよホールデンはアントリーニ先生の行為にホモフォビアのごとく拒絶反応を示しているのである。
もうひとつホールデンに対する根本的な疑問を最後に挙げるなら、ホールデンは序盤で「僕はとてつもない嘘つきなんだ。まったく救いがたいくらい」と述べている点だ。時に饒舌極まる彼の語りが、一体どこまで本当のことを言っているのか、しかも誰に話しかけているのか、最後までよくわからなかった。まあ明日は村上春樹+柴田元幸『翻訳夜話2 サリンジャー戦記』を読むので、そこで色々と書いてあるだろう。自分の読んだ印象についても修正されるかもしれない。